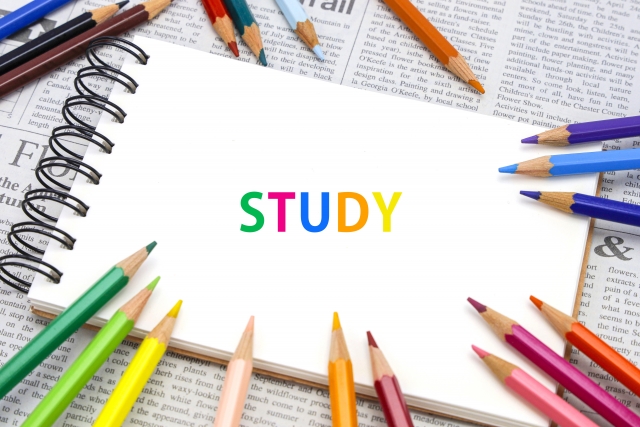下宿生活している大学生の娘に生活費を贈与した場合に、この生活費は贈与税の対象となるのでしょうか?
ここでは、生活費を贈与した場合の贈与税の取扱いについてご説明いたします。
生活費は贈与税非課税?
扶養義務者相互間において生活費に充てるために贈与した財産のうち、通常必要と認められるものは贈与税は非課税とされています。
この点については、相続税法において次のように規定されています。
(贈与税の非課税財産)
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの
扶養義務者とは
扶養義務者の定義については、相続税法において次のように規定されています。
(定義)
第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 扶養義務者 配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。
具体的には、次の者が扶養義務者として取り扱うこととされています。(相基通1の2-1)
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
生活費とは
生活費の意義については、相続税法基本通達において次のように記載されています。
(「生活費」の意義)
21の3-3 法第21条の3第1項第2号に規定する「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除く。)をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除く。)を含むものとして取り扱うものとする。
教育費とは
教育費の意義については、相続税法基本通達において次のように記載されています。
(「教育費」の意義」)
21の3-4 法第21条の3第1項第2号に規定する「教育費」とは、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないのであるから留意する。
通常必要と認められるものとは
贈与した生活費や教育費について、贈与税が非課税となる通常必要と認められるものとは、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうこととされています。(相基通21の3-6)
また、「生活費又は教育費に充てるためにした贈与」が前提となるため、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与した場合において、その財産が預貯金となっている場合や、株式や家屋の購入に充てられた場合には、贈与税の課税対象となります。
生活費又は教育費を贈与する場合には、常識的な金額で、必要な都度贈与することが贈与税非課税のポイントになるものと考えます。
なお、扶養義務の履行のために供された金品については贈与とはいえないこととされています。(平成22年11月19日裁決)
この点については、所得税法の非課税の規定において、所得税法9条1項15号「扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品」、17号「相続、遺贈又は個人からの贈与により取得するもの(相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により相続、遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。)」として、別規定を設けていることが根拠になっているものと考えます。
つまり、扶養義務の履行の範囲内のものは贈与ではなく、所得税非課税となります。
扶養義務の履行の範囲を超えるものについては贈与となり、「通常必要と認められるもの」であれば贈与税非課税となります。
【参考】結婚費用について
婚姻後の生活を営むために、通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の購入資金を親から贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合には、贈与税を課税しないこととされています。【国税庁Q&A2-1】
また、子の結婚式・披露宴の費用を親が負担した場合には、招待客との関係や地域の慣習などの諸事情に応じて親が負担することとなっている場合には、そもそも贈与には当たらないこととされています。【国税庁Q&A2-2】
なお、個人から受ける結婚祝等の金品については、贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては贈与税を課税しないこととされています。
この点については、相続税法基本通達において次のように記載されています。
(社交上必要と認められる香典等の非課税の取扱い)
21の3-9 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする。
【参考】出産費用について
出産に要する費用で、検査・検診代、分娩・入院費に充てるために親から贈与を受けた場合には、これらは治療費に準ずるものであることから、保険金等により補填される部分を除き、贈与税を課税しないこととされています。
また、新生児のための寝具、産着等ベビー用品の購入費に充てるため金銭の贈与を受けた場合についても、購入費に実際に充てられた部分については贈与税を課税しないこととされています。【国税庁Q&A3-1】
【参考】家賃負担について
子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合には、子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には贈与税を課税しないこととされています。【国税庁Q&A5-1】
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。