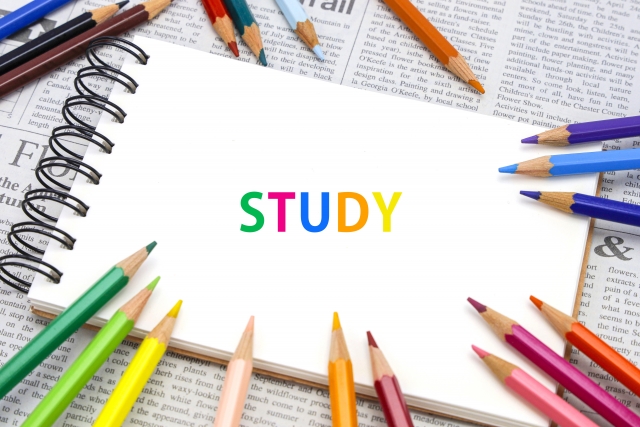非適格合併により企業を買収した買手側については、調整勘定について一定の処理が必要となります。
ここでは、非適格合併における調整勘定の処理についてご説明いたします。
資産調整勘定について
非適格合併により被合併法人から資産又は負債の移転を受けた場合において、非適格合併等対価額(非適格合併により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額)が、移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額を超えるときは、その超える部分の金額が資産調整勘定の金額となります。(法62の8Ⅰ)
この資産調整勘定については、当初計上額を60で除した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を当該事業年度において減額しなければならないこととされています。(法62の8Ⅳ)
また、この減額した金額については、減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入することになります。(法62の8Ⅴ)
負債調整勘定について
負債調整勘定については、退職給与負債調整勘定、短期重要負債調整勘定、差額負債調整勘定の3つが規定されています。(法62の8Ⅱ)
退職給与負債調整勘定
非適格合併に伴い、被合併法人から引継ぎを受けた従業者につき、退職給与債務引受けをした場合における退職給与債務引受額(法令123の10Ⅶ)が、退職給与負債調整勘定の金額となります。(法62の8Ⅱ①)
この退職給与負債調整勘定については、退職給与引受従業者が退職その他の事由により従業者でなくなった場合又は退職給与引受従業者に退職給与を支給する場合には、負債調整勘定のうち、これらの
退職給与引受従業者に係る部分の金額として一定の金額(法令123の10Ⅹ)を減額しなければならないこととされています。(法62の8Ⅵ①)
また、この減額した金額については、減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することになります。(法62の8Ⅷ)
短期重要負債調整勘定
非適格合併に伴い、被合併法人から移転を受けた事業に係る将来の債務(その事業の利益に重大な影響を与えるものに限り、退職給与債務引受及び既に履行すべきことが確定しているものを除く)で、その履行が非適格合併の日からおおむね3年以内に見込まれるものについて、その履行に係る負担をの引受けをした場合における短期重要債務見込額が、短期重要負債調整勘定の金額となります。(法62の8Ⅱ②)
この短期重要負債調整勘定については、短期重要債務見込額に係る損失が生じ、もしくは非適格合併の日から3年を経過した場合、又は自己を被合併法人とする非適格合併を行う場合、もしくは残余財産が確定した場合には、短期重要負債調整勘定のうち、その損失の額に相当する金額(3年経過した場合、合併を行う場合、残余財産が確定した場合にあっては短期重要負債調整勘定の金額)を減額しなければならないこととされています。(法62の8Ⅵ②)
また、この減額した金額については、減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することになります。(法62の8Ⅷ)
差額負債調整勘定
非適格合併により被合併法人から資産又は負債の移転を受けた場合において、非適格合併等対価額(非適格合併により交付した金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額)が、移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額満たないときは、その満たない部分の金額が差額負債調整勘定の金額となります。(法62の8Ⅲ)
この差額負債調整勘定については、当初計上額を60で除した金額に当該事業年度の月数を乗じて計算した金額を当該事業年度において減額しなければならないこととされています。(法62の8Ⅶ)
また、この減額した金額については、減額すべきこととなった日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入することになります。(法62の8Ⅷ)
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。