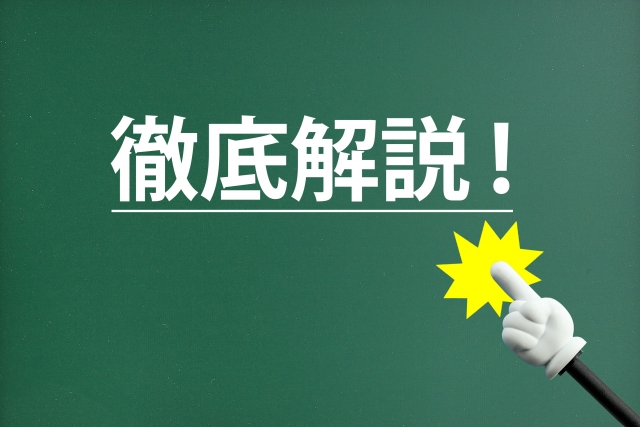転勤に伴い、これまで居住用として所有していた分譲マンションの1室を賃貸物件として貸し出すことがあります。
そして、他人に貸すことによって退去後の原状回復費用が思ったよりも高くついたため、知人に低賃料で貸付けるといったケースがあります。
今回は、このケースにおける所得税の取扱いについてご説明いたします。
使用貸借は不動産所得とならない?損益通算できない?
まずは、不動産所得の定義について確認したいと思います。
不動産所得の定義については、所得税法において次のように規定されています。
(不動産所得)
第二十六条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
そして、この「不動産の貸付けによる所得」については、平成17年7月8日東京地裁判決において、次のように判示されています。
判示
「不動産等の貸付けによる所得とは、当事者の一方が相手方から不動産等を使用収益させて、その対価を得ることを目的とする行為から生ずる所得をいうものと解されるから、不動産等の賃貸借から生ずる賃料はこれに該当するが、対価を伴わない使用貸借については、借主からの金員の交付等があっても、それは、当該不動産等の経費の一部の支払にすぎず、不動産等の貸付けによる所得には該当しないと解すべきである。」
「また、必要経費についても、使用貸借契約に基づき貸し付けている資産に関する固定資産税等や借入金利子及び減価償却費は、不動産所得を生ずべき業務に供されたことによって生じたものとはいえないから、不動産所得の必要経費に該当しないので、不動産所得の金額の計算上必要経費には算入されないというべきである。」
つまり、使用貸借による不動産の貸付けは不動産所得にはならず、使用貸借で赤字になっても損益通算できないものと考えられます。
使用貸借?賃貸借?
不動産の貸付けに際し、毎月定額の金銭の授受がなされていても、公租公課を負担する程度のものであれば、「対価を得る目的とする行為」とはいえないため、使用貸借と認定されます。
使用貸借の定義については、民法593条によって次のように規定されています。
(使用貸借)
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
また、使用貸借における借主については、次のように通常の必要費を負担する旨、規定されています。
(借用物の費用の負担)
第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。
つまり、毎月定額の金銭の授受がなされても、その金額が少額で、借主が負担すべき通常の必要費の範囲内のものであれば、その金銭は「対価」ではなく、「必要費の補填」と考えられ、使用貸借と認定されることになります。
ここでの「通常の必要費の範囲内」が具体的にいくらなのかについては、明確な規定はありません。
参考までに、平成8年3月29日裁決において、賃貸借契約書がなく、地代の取り決めもなされず、結果的に固定資産税の1.7倍以上の金銭の授受がなされているだけでは、「対価を得る目的とする行為」とはいえないため、使用貸借と認めるのが相当であると示されています。
賃貸借を使用貸借と認定されないようにするためには、賃貸借契約書を作成し、契約に基づき賃料の授受を行い、賃料の設定金額は最低でも固定資産税の2~3倍にする必要があるものと考えます。
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。