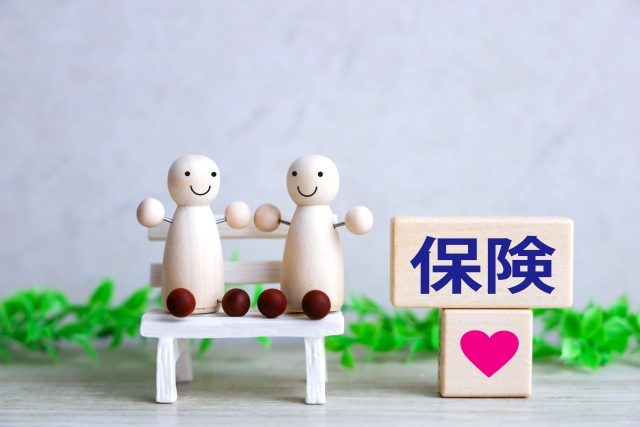生命保険契約を投資の一部と考えて、積立利率が高い外貨建生命保険契約を締結するケースが増えてきました。そして、最近の円安の影響により、その外貨建生命保険を解約して、利益を確定する動きがみられます。
ここでは、外貨建保険の税金の取扱いとして、特に所得税との関係についてご説明いたします。
外貨建取引の換算について
外貨建保険を解約し、所得を得た場合には、所得税が課せられることになります。
この場合の所得区分は、為替差損益を含めて「一時所得」となります。
単に外貨を円に換えたときに生じる為替差益については、「雑所得」に区分されますが、生命保険の解約に伴い確定する為替変動による利益については、為替差益として別建てで認識するのではなく、一時所得に含まれることになります。
その根拠としては、外貨建取引の換算について規定している所得税法57の3があります。
(外貨建取引の換算)
第五十七条の三 居住者が、外貨建取引(外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引をいう。以下この条において同じ。)を行つた場合には、当該外貨建取引の金額の円換算額(外国通貨で表示された金額を本邦通貨表示の金額に換算した金額をいう。次項において同じ。)は当該外貨建取引を行つた時における外国為替の売買相場により換算した金額として、その者の各年分の各種所得の金額を計算するものとする。
つまり、外貨建保険を解約した時における為替レートで一時所得の金額を計算するため、外貨建保険の解約返戻金を外貨で受け取っても円で受け取っても、所得金額の計算自体は変わらないことになります。
また、法人税法における「外貨建預金等の期末時換算」のような規定は、所得税法にはないため、仮に解約返戻金を外貨で受け取り、年末まで保有していても年末レートにおける為替差損益を認識することはありません
【参考】相続で取得した外貨預金における為替差益について
被相続人が生前に外貨預金を預け入れ、相続後に相続人が外貨預金を円に換えた場合の為替差益については、相続人の雑所得として所得税が課せれられるものと考えます。
この場合の為替差損益については、被相続人が預け入れた時の為替レートと相続人が円に換えたときの為替レートの差額による認識するものと考えます。
その根拠としては、所得税法67の4の規定が考えられます。
第六十七条の四 居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。
つまり、相続それ自体は外貨建て取引ではないため、相続時点では為替差損益を認識せず、相続人が引き続き外貨預金を所有していたものとみなされるため、相続人が外貨預金の預入時のレートをそのまま引き継ぐことになります。その後に外貨を円に換えた時点で為替差損益を認識し、相続人の雑所得として課税されるものと考えます。
なお、相続税の計算においては、相続時点での為替レートで相続税評価を行います。(財産評価基本通達4-3)
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。