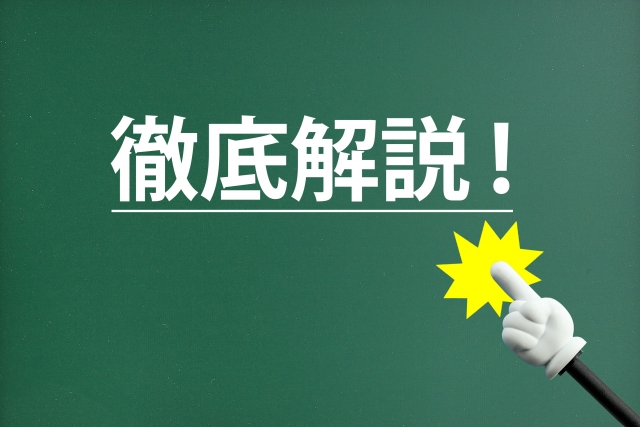節税の手法として、会社が所有する有価証券の含み損を実現させるために、有価証券を売却する方法が考えられます。
しかし、所有する有価証券の含み損は一時的なもので、将来的に価額が回復する見込みであるため、いったん売却してから再購入するといったクロス取引が行われるケースがあります。
今回は、このクロス取引の税務についてご説明いたします。
なお、売買目的有価証券は、期末の価額と帳簿価額との差額については、強制的に評価替えが行われ、評価損益を認識することとなっている(法61の3Ⅱ)ため、クロス取引の税務の対象外となります。
有価証券の評価損について
有価証券の評価損については、原則として費用にならないこととされています。(法33Ⅰ)
しかし、有価証券の価額が著しく低下した場合には、評価損について費用となる旨、規定されています。(法33Ⅱ、法令68Ⅰ②イ)
この場合の「著しく低下した場合」については、期末の価額が帳簿価額よりも50%以上下落し、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないこととされています。(法基通9-1-7)
クロス取引の税務の取扱いについて
法人が行うクロス取引
会社が同一の有価証券(売買目的有価証券を除く)を売却の直後に購入するといったように、クロス取引に該当する場合には、その売却はなかったものとして取り扱うこととされています。
この点については、法人税法基本通達において次のように記載されています。
(売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引)
2-1-23の4 同一の有価証券(法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券を除く。)が売却の直後に購入された場合において、その売却先から売却をした有価証券の買戻し又は再購入(証券業者等に売却の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該証券業者等からの購入又は当該証券業者等に購入の媒介、取次ぎ若しくは代理の委託をしている場合の当該購入を含む。)をする同時の契約があるときは、当該売却をした有価証券のうち当該買戻し又は再購入をした部分は、その売却がなかったものとして取り扱う。
(注)
1 同時の契約がない場合であっても、これらの契約があらかじめ予定されたものであり、かつ、売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されているとき又はこれらの価額が売却の決済日と購入の決済日との間に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されているときは、同時の契約があるものとして取り扱う。
2 本文の適用を受ける取引に伴い支出する委託手数料その他の費用は、当該有価証券の取得価額に含めない。
3 購入の直後に売却が行われた場合の当該購入についても同様に取り扱う。
ここで注意すべきは、クロス取引に該当する場合としては、同一の有価証券の売却と購入について、同時の契約に限られていないことです。
金融商品会計に関する実務指針42では、クロス取引について次のように記載されています。
クロス取引
42.金融資産を売却した直後に同一の金融資産を購入した場合又は金融資産を購入した直後に同一の金融資産を売却した場合で、譲渡人が譲受人から譲渡した金融資産を再購入又は回収する同時の契約があるときは、金融商品会計基準第9項(3)の金融資産の消滅の認識要件を満たさないので、売買として処理しない。したがって、購入の直後に売却された場合、当該購入金融資産と保有する同一銘柄との簿価通算はできない。譲渡価格と購入価格が同一の場合、又は譲渡の決済日と購入の決済日とに期間があり当該期間に係る金利調整が行われた価格である場合、譲渡人が譲受人から再購入又は回収する同時の
契約があると推定する。
また、金融商品会計に関するQ&AQ12では、クロス取引について次にように記載されています。
例えば、金融資産を売却した後に同一の金融資産を同一数量若しくはほとんど同一数量購入した場合又は金融資産を購入した後に同一の金融資産を売却した場合で、かつ、譲渡価格と購入価格が同一の場合、又は譲渡の決済日と購入の決済日の期間に係る金利調整が行われた価格である場合には、譲渡人が譲受人から再購入又は回収する同時の契約があると推定されます(実務指針第42項)ので、金融資産の消滅の認識要件を満たさず売却処理は認められないと考えられます。また、例えば、金融資産を売却した直後(5営業日までは直後と考えられます。)に同一の金融資産を購入した場合又は金融資産を購入した直後に同一の金融資産を売却した場合であって、それらの取引における譲渡価格と購入価格がともに取引時の時価であるからといって必ずしも売却処理が認められるわけではなく、実質的に相対取引になっていると解される等、取引の実態によっては売却処理が否定されることもあります。
個人が行うクロス取引について
個人が上場・店頭売買株式を売却するとともに直ちに再取得する場合には、会社がクロス取引を行う場合のような規制はなく、株式の譲渡として譲渡損の計上が認められます。(個人が上場・店頭売買株式を売却するとともに直ちに再取得する場合の当該売却に係る源泉分離課税の適用について(法令解釈通達))
なお、同一の日に同一の銘柄を売却購入することを前提とした規定として、措置法施行令25の10の2Ⅰ③の規定があります。
(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例)
措置法施行令
第二十五条の十の二
三 一の特定口座において一の日に二回以上にわたつて同一銘柄の特定口座内保管上場株式等の譲渡があつた場合には、当該一の日におけるこれらの譲渡については、これらの譲渡のうち最後の譲渡の時にこれらの譲渡があつたものとみなして、所得税法施行令第百十八条の規定を適用する。
(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等)
所得税法施行令
第百十八条 居住者が法第四十八条第三項(譲渡所得の基因となる有価証券の取得費等の計算)に規定する二回以上にわたつて取得した同一銘柄の有価証券で雑所得又は譲渡所得の基因となるものを譲渡した場合には、その譲渡につき法第三十七条第一項(必要経費)の規定によりその者のその譲渡の日の属する年分の雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額又は法第三十八条第一項(譲渡所得の金額の計算上控除する取得費)の規定によりその者の当該年分の譲渡所得の金額の計算上取得費に算入する金額は、当該有価証券を最初に取得した時(その後既に当該有価証券の譲渡をしている場合には、直前の譲渡の時。以下この項において同じ。)から当該譲渡の時までの期間を基礎として、当該最初に取得した時において有していた当該有価証券及び当該期間内に取得した当該有価証券につき第百五条第一項第一号(総平均法)に掲げる総平均法に準ずる方法によつて算出した一単位当たりの金額により計算した金額とする。
つまり、特定口座において、同一銘柄の株式を同一の日に取得と売却を繰り返した場合の取得費の計算においては、一旦取得をすべて行ってからその後に売却をしたものとして取り扱うことになります。
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。