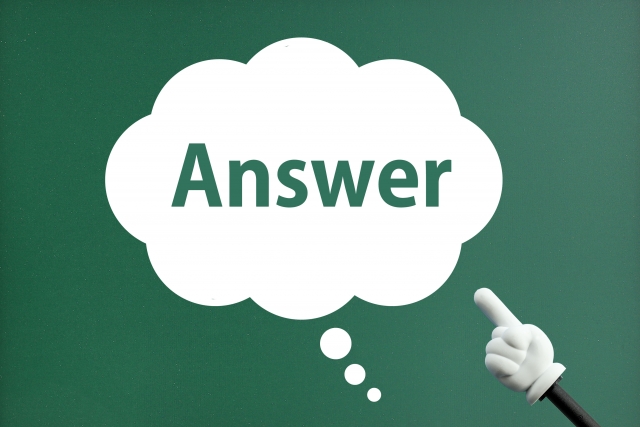従業員の食事代を会社が負担した場合には経費になります。
経費のうち、「給与等」「交際費等」「福利厚生費」のいずれに該当するかによって取り扱いが異なるため、費用の区分については検討する必要があります。
給与等に該当する場合には、源泉所得税の納付義務が発生します。
交際費等に該当する場合には、経費として認められる金額に上限があり、上限額を超える分については経費として計上することができません。
ここでは、従業員の食事代が、経費のうち「福利厚生費」「給与等」「交際費等」のいずれに該当するのかについてご説明いたします。
「給与等」と「交際費等・福利厚生費」の区分ついて
まずはじめに、給与等に該当するか否かについてご説明いたします。
●残業時の食事について
残業している従業員に対し、時間外勤務をすることにより支給する食事については、給与課税しないとされています。(所得税法基本通達36-24)
ここで注意すべきことは、支給する内容が「食事」であって、「食事代」ではないということです。つまり会社が食事代として金銭を支給した場合には、深夜勤務の夜食で1回300円以下のものを除き、給与課税されます。(質疑応答事例 源泉所得税)
●昼食について
従業員に対し支給する食事(残業時の食事を除く)について、従業員から食事の価額の50%以上を徴収し、会社の実質負担額が月額3,500円(税抜き)以下であるときは、給与課税しないとされています。(所得税法基本通達36-38の2、平成元年1月30日直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて(法令解釈通達)2」)
ここで注意すべきことは、支給する内容が「食事」であって、「食事代」ではないということです。つまり会社が食事代として金銭を支給した場合には、深夜勤務の夜食で1回300円以下のものを除き、給与課税されます。(質疑応答事例 源泉所得税)
「交際費等」と「福利厚生費」の区分について
上記で給与課税しないとされた場合において、会社においても給与として経理しなければ、法人税においても給与として取り扱わないものとされています。(法人税法基本通達9-2-10)
それでは、給与課税しないとされた場合に、交際費等に該当するか否かについてご説明いたします。
従業員に対する慰安の目的で負担する食事代については、たとえ相手方が従業員であっても、一定の要件を満たさない場合には、交際費等に該当します。(措置法通達61の4(1)-22)
ここでの一定の要件とは、「従業員におおむね一律」かつ「通常の飲食」になります。(措置法通達61の4(1)-10(1))
つまり、特定の役員や従業員にだけ支給する飲食代、通常の範囲を超える飲食代については、交際費等に該当することになります。
【参考】食事の現物給与における社会保険
現物で支給される給与が食事や住宅である場合には、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(厚生労働省告示)に定められた額に基づいて通貨に換算し、自社製品等その他のものについては、時価に換算し、その価額を報酬に合算のうえ、標準報酬月額を算出します。
現物給与のうち、食事を支給する場合には、原則として、厚生労働省告示額から従業員負担額を引いた価額が標準報酬月額に合算されます。
しかし、例外として、厚生労働省告示額の3分の2以上を従業員が負担している場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱われることになっています。
この点については、通達において次のように記載されています。
○厚生労働大臣が定める現物給与の価額の取扱いについて
(平成24年1月31日)
(/基労徴発0131第1号/保保発0131第1号/年管管発0131第1号/)
(都道府県労働局総務部(労働保険徴収部)長あて労働基準局労災補償部労働保険徴収課長・保険局保険課長・年金局事業管理課長通知)
標記については、今般、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の全部を改正する件」(平成24年厚生労働省告示第36号)が告示され、その内容については、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)」(平成24年1月31日付け基発0131第1号)により通知したところである。
これらの事務の取扱いについては、下記のとおりであるので、貴職におかれては、関係職員に周知の上、遺漏なきよう取り計らわれたい。
1.食事で支払われる報酬等
(2) 社会保険における取扱い
昭和33年7月5日付け内かんにより、告示額の3分の2以上に相当する額を食費として徴収されている場合には、現物による食事の供与はないものとして取り扱うこと。
なお、この例外的な取扱いは、あくまでも食事の現物給与に限られ、住宅による現物給与については適用がありませんのでご注意ください。
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。