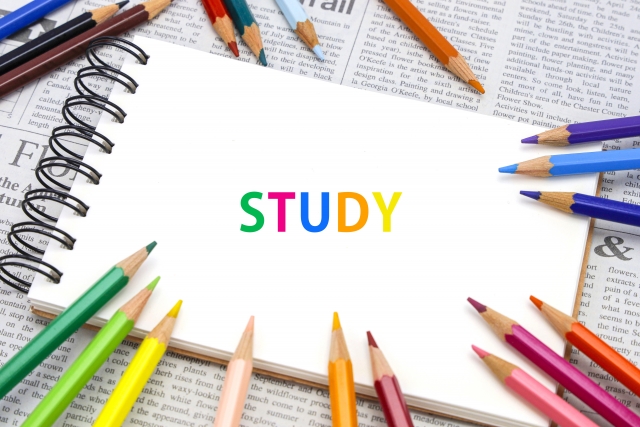役員または従業員が死亡した場合において、会社が弔慰金とは別に香典を遺族に支払うケースがあります。
今回は、会社が弔慰金とは別に香典を支払った場合における、会社側と遺族側の税務の取扱いについてご説明いたします。
会社側(支払側)
弔慰金については、社内規程において、業務上の死亡である場合には賞与以外の普通給与の3年分、業務上の死亡出ない場合には半年分と定めるケースが一般的です。
大半の会社においては、相続税法基本通達3-20に沿った内容で弔慰金についての社内規程を定めているものと思われます。
普通給与の3年分や半年分といった金額は、あくまでも相続税においてみなし相続財産の対象となるか否かの基準であって、法人税においては、弔慰金の限度額を定めた規定はありません。
そのため、弔慰金の金額について、他の役員退職金とあわせて、「不相当に高額な部分」がある場合には損金不算入とされるリスクがあります。(法34Ⅱ、法令70②)
しかし、実務においては、過去の裁決や判例において、相続税法基本通達3-20の範囲内における弔慰金について過大として損金不算入とされたケースがありません。
事実上、法人税においては、相続税法基本通達3-20を準用しているものと考えられます。
弔慰金とは別に香典を支払う場合には、社内規程において、弔慰金と香典を明確に区分して記載しておく必要があるものと考えます。
福利厚生費と交際費の区分について、法人税法基本通達において次のように記載されています。
(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
遺族側(受取側)
遺族が受け取る香典については、会社からのものについては、所得税法基本通達9-23により、社会通念上相当と認められるものについては、所得税法施行令30③に該当し、所得税は非課税となります。
一方、個人からの香典については、相続税法基本通達21の3-9により、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税は非課税となります。
なお、香典は喪主に対しての贈与であり、そもそも相続財産には該当しないため、相続税の対象とはなりません。
次に、遺族が受け取る弔慰金については、相続税法基本通達3-20の定めがあるだけで、その他に法令や通達はありません。
(弔慰金等の取扱い)
3-20 被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金、花輪代、葬祭料等(以下「弔慰金等」という。)については、3-18及び3-19に該当すると認められるものを除き、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に該当するものとして取り扱うものとする。
(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいう。以下同じ。)の3年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が3年分を超えるときはその金額)に相当する金額
(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の普通給与の半年分(遺族の受ける弔慰金等の合計額のうち3-23に掲げるものからなる部分の金額が半年分を超えるときはその金額)に相当する金額
相続税法基本通達3-20では、弔慰金に相当する金額として、業務上の死亡である場合には賞与以外の普通給与の3年分、業務上の死亡出ない場合には半年分とし、その金額を超える部分は、退職手当金としてみなし相続財産に該当し、相続税の課税対象とすることとされています。
この通達はあくまでも相続税の課税対象となるか否かについての取扱いを記載したものであって、相続税の課税対象とならない弔慰金を受け取ったことによる贈与税や所得税(一時所得)については、何ら法令や通達はありません。
しかし、質疑応答事例「贈与税の対象とならない弔慰金等」において、相続税法基本通達3-20により弔慰金等に相当する金額については、香典と同様に取り扱うこととされています。
なお、元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金については、相続税法基本通達3-20に記載する「雇用主等から受ける弔慰金」に該当しないため、法人からの贈与として一時所得に該当するものとされています。(質疑応答事例「生前に退職している被相続人の死亡により元の勤務先から支払いを受ける特別弔慰金等」)
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。