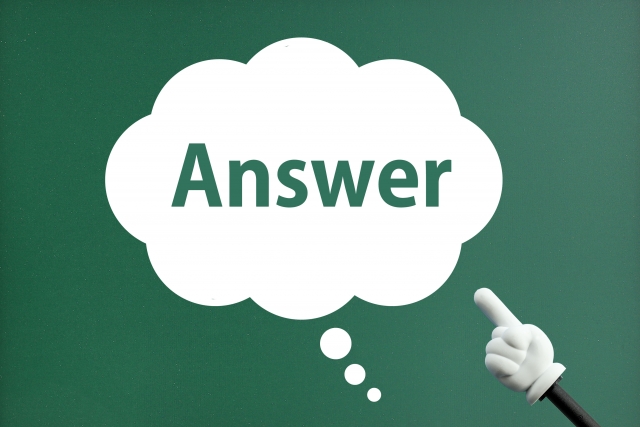個人事業主が店舗併用住宅(1階店舗、2階住宅で事業用割合50%)を売却した場合の税金の取扱いについてご説明いたします。
所得税の取扱い
事業用資産であっても、資産を譲渡した場合には、基本的には「譲渡所得」として課税されることになります。
そして、土地や建物を譲渡した場合の譲渡所得の金額は次のように計算することになります。(措置法)
課税譲渡所得金額=収入金額△取得費△譲渡費用△特別控除額
取得費について
建物の取得費については、建物の購入代金などの合計額から減価償却費相当額を控除した金額となります。
そして、この「減価償却費相当額」については、事業に使われていた部分と事業に使われていなかった部分で計算方法が異なります。
そのため、建物の譲渡所得における「取得費」については、店舗部分と住宅部分に分けて算出する必要があります。
非業務用建物の減価償却費相当額について
建物の耐用年数の1.5倍の年数(1年未満の端数は切り捨てます。)に対応する旧定額法の償却率で求めた1年当たりの減価償却費相当額にその建物を取得してから売るまでの経過年数を乗じて計算します。(所得税法施行令85)
建物の取得価額×0.9×償却率× 経過年数(※1)= 減価償却費相当額(※2)
※1経過年数の6か月以上の端数は1年とし、6か月未満の端数は切り捨てます。
※2建物の取得価額の95%を限度とします。
仲介手数料について
土地や建物を購入した際に、不動産仲介業者に支払った仲介手数料については、土地及び建物のそれぞれの取得価額に算入することになります。
所得税法において、購入手数料は資産の購入代価として減価償却資産の取得価額に算入することと規定されており(所49Ⅱ、所令126Ⅰ①イ)、仲介手数料はこの購入手数料に該当することから必要経費とすることはできず、資産の取得価額に算入することになります。
不動産取得税・登録免許税について
業務用の土地建物に係る不動産取得税や登録免許税については、必要経費に算入することとされています。(所基通37-5.49-3)
一方、非業務用の土地建物に係る不動産取得税や登録免許税については、土地建物の取得費に算入することとされています。(所基通38-9)
譲渡所得の課税の特例について
店舗併用住宅の譲渡については、店舗部分と住宅部分の2つの資産の譲渡と考えられるため、店舗部分の譲渡については「特定の事業用資産の買換え特例」の適用を受け、住宅部分の譲渡については「居住用財産の譲渡の3,000万円の特別控除」の適用を受けることができます。(措通35-1)
消費税の取扱い
消費税の課税の対象については、消費税法において次のように規定されています。
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。
さらに、「事業として」の意義については、消費税法基本通達において次のように記載されています。
(事業としての意義)
5-1-1 法第2条第1項第8号《資産の譲渡等の意義》に規定する「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供が反復、継続、独立して行われることをいう。
(注)1 個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は、「事業として」には該当しない。
上記の規定により、消費税の課税対象となる部分は、店舗部分の土地建物の譲渡ということになります。
住宅部分の土地建物については、「事業として」には該当しないことから、消費税の課税対象とはなりません。
事業供用割合を50%とした場合には、建物の譲渡代金の半分が課税売上となり、土地の譲渡代金の半分が非課税売上となります。
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。