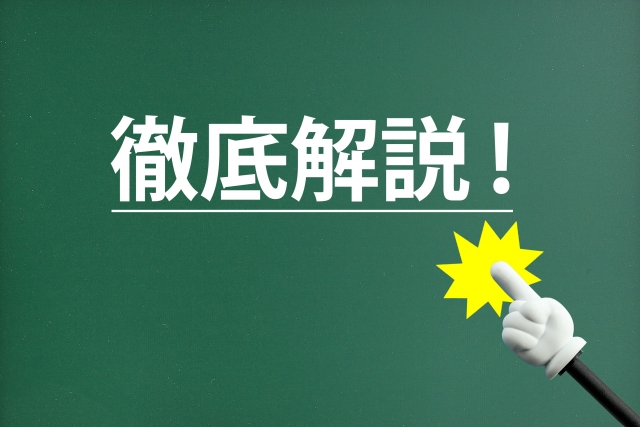リース取引については、法人税法上のリース取引(ファイナンスリース取引)と賃貸借取引(オペレーティングリース取引)に区分されます。
そして、法人税法上のリース取引については、さらに所有権移転ファイナンスリース取引と所有権移転外ファイナンスリース取引に区分されます。
今回は、オペレーティングリース取引、所有権移転ファイナンスリース取引、所有権移転外ファイナンスリース取引について、それぞれの法人税の取扱いについてご説明いたします。
法人税法上のリース取引とは?
法人税法上のリース取引に該当する場合には、リース資産の引渡しの時にリース資産の売買があったものとして処理されることになります。(法64の2Ⅰ)
そして、法人税法上のリース取引とは、中途解約不能要件とフルペイアウト要件の両方を満たす取引と規定されています。
(リース取引に係る所得の金額の計算)
第六十四条の二 内国法人がリース取引を行つた場合には、そのリース取引の目的となる資産(以下この項において「リース資産」という。)の賃貸人から賃借人への引渡しの時に当該リース資産の売買があつたものとして、当該賃貸人又は賃借人である内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。
3 前二項に規定するリース取引とは、資産の賃貸借(所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるものを除く。)で、次に掲げる要件に該当するものをいう。
一 当該賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途においてその解除をすることができないものであること又はこれに準ずるものであること。
二 当該賃貸借に係る賃借人が当該賃貸借に係る資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受することができ、かつ、当該資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであること。
そして、リース料総額が見積取得価額の9割を超える場合には、フルペイアウト要件を満たすこととされています。
この点については、法人税法施行令において次のように規定されています。
(リース取引の範囲)
第百三十一条の二
2 資産の賃貸借につき、その賃貸借期間(当該資産の賃貸借に係る契約の解除をすることができないものとされている期間に限る。)において賃借人が支払う賃借料の金額の合計額がその資産の取得のために通常要する価額(当該資産を事業の用に供するために要する費用の額を含む。)のおおむね百分の九十に相当する金額を超える場合には、当該資産の賃貸借は、法第六十四条の二第三項第二号の資産の使用に伴つて生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものであることに該当するものとする。
オペレーティングリース取引
中途解約不能要件またはフルペイアウト要件のいずれかを満たさない場合には、法人税法上のリース取引に該当せず、オペレーティングリース取引に該当することになります。
オペレーティングリース取引の場合には、資産の賃貸借に準じて、リース料の支払の都度費用処理を行うことになります。
法人税法上のリース取引(所有権移転外ファイナンスリース取引)
所有権移転外ファイナンスリース取引とは?
法人税法上のリース取引のうち、次のいずれにも該当しないものが所有権移転外ファイナンスリース取引とされています。(法令48の2Ⅴ⑤、法基通7-6の2-1)
1 リース期間の終了時または中途において、そのリース取引に係る契約において定められているリース取引の目的とされている資産(以下「リース資産」といいます。)が無償または名目的な対価の額でそのリース取引に係る賃借人に譲渡されるものであること。
2 リース期間の終了後、無償と変わらない名目的な再リース料によって再リースをすることがリース契約において定められているものであること。
3 リース期間の終了時または中途においてリース資産を著しく有利な価額で買い取る権利が賃借人に与えられているものであること。
4 賃借人の特別な注文によって製作される機械装置のようにリース資産がその使用可能期間中その賃借人によってのみ使用されると見込まれるものであることまたは建築用足場材のようにリース資産の識別が困難であると認められるものであること。
5 賃貸人に対してリース資産の取得資金の全部または一部を貸し付けている金融機関等が、賃借人から資金を受け入れ、その資金をしてその賃借人のリース取引等の債務のうちその賃貸人の借入金の元利に対応する部分の引受けをする構造になっているものであること。
6 リース期間がリース資産の法定耐用年数に比して相当短いもの(賃借人の法人税の負担を著しく軽減することになると認められるものに限ります。)であること。
所有権移転外ファイナンスリース取引の法人税の取扱い
所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、償却方法がリース期間定額法と規定されています。(法令48の2Ⅰ⑥)
リース期間定額法の償却限度額については、次の算式により計算した金額になります。
リース期間定額法の償却限度額
= ((リース資産の取得価額 - 残価保証額) / リース期間の月数) × その事業年度におけるそのリース期間の月数
※「残価保証額」とは、リース期間終了の時にリース資産の処分価額が所有権移転外リース取引に係る契約において定められている保証額に満たない場合にその満たない部分の金額を賃借人が支払うこととされている場合におけるその保証額をいいます。
法人税法上のリース取引(所有権移転ファイナンスリース取引)
所有権移転ファイナンスリース取引とは?
法人税法上のリース取引のうち、所有権移転外ファイナンスリース取引に該当しないものをいいます。
所有権移転ファイナンスリース取引との法人税の取扱い
所有権移転リース取引により賃借人が取得したものとされるリース資産である減価償却資産については、資産の種類に応じて選定している償却方法によって減価償却費を計上することになります。
オープンエンド方式によるオペレーティングリース取引について
オープンエンド方式とは、最終的な処分価値を最初の段階で明示して、その分だけリース料の支払総額を減らす方式をいいます。
このオープンエンド方式を利用することで、フルペイアウト要件である「リース料総額が見積取得価額の9割を超える」ことを回避し、オペレーティングリース取引とすることが考えられます。
しかし、「リース料総額が見積取得価額の9割」という形式基準は、あくまでも9割を超えた場合にはフルペイアウト要件を満たすと規定しているだけで、9割以下はフルペイアウト要件を満たさないとは規定していません。リース資産について購入が前提となっている場合には、たとえ9割超でなくても法人税法上のリース取引に該当するものと考えます。
この点については、令和2年3月23日裁決において次のように示されています。
「請求人は、本件各リース物件について、購入することを前提に各取引先から見積りを取るなどした後、請求人の工場に搬入されて運転を開始する中で、購入代金の支払前に本件各リース契約が締結されたことが認められ、また、本件各リース物件の耐用年数(8年)に比して短期間のリース期間(12か月)であるにもかかわらず、当該リース期間に係るリース料の総額が本件各リース物件の取得のために通常要する価額の100分の90に近い水準に設定されていること等から、請求人が本件各リース物件を契約期間満了後に購入することが本件各リース契約の前提となっていたことがうかがえる。・・・そうすると、本件各リース物件の本件各見積取得価額に占めるリース料金の総額の割合を前提に、本件各リース契約の契約内容やその実態を併せ検討すれば、その割合は100分の90を超えないものの、本件各リース契約は、請求人が資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされているものと認められるとともに、請求人が当該資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができるものと認められる。」
最後に
弊所は、お客様と共に悩み、考え、お客様の成長と発展に貢献できる経営パートナーとしてのサービスをご提供いたします。
お気軽に当事務所にお問い合わせください。
⇩
「税理士小林繁樹事務所のホームページ」
免責事項
本記事を掲載するにあたって、情報の正確性について細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではなく、何らの責任を負うものではありません。
必ずしも内容の全部を表現したものではないため、実務における判断を行う際は、必ず専門家にご相談ください。